ことば遊びのパングラム(pangram)はさまざまな言語で行なわれていますが、日本語によるパングラムを私は「かなパズル」と名づけました。その理由を、日本では「いろは歌」が代名詞にもなっているこのことば遊びの紹介も兼ねつつ、ご説明したいと思います。
パングラムとは
まず、パングラムは「当該言語の基底をなす一定数の文字を、できるだけ重複を避けながらもれなく用いて、詩歌や文を作る」ことば遊びと定義できます。「当該言語の基底をなす一定数の文字」とは、たとえば英語ならA~Zのアルファベット26字、現在の日本語ならあ~んのかな46字ということです。
日本では「いろは歌」が断トツの知名度を誇りますが、世界でいちばん有名なパングラムといえば、英語の「The quick brown fox jumps over the lazy dog.」でしょう。フォントのサンプル文などで使用されることもあり、ご覧になったことがある方もいるのではないでしょうか。
*
パングラムの条件に思いを巡らせれば、ことばの扱いを不自由にする制約であることは明白です。言語的な縛りをかけ、表現-意味内容が不自然になるよう構造的に仕向けている。
してみると、このことば遊びの目的も自ずと明らかでしょう。つまり不自然さへと方向づけられているなか、それに抗ってまっとうな詩文になるべく努めるところに、知的なことばのゲームたる意義が生まれるわけです。
*
要するに、パングラムにおいてはことばづかいから文意から一字一句にわたって常識的に無理なくまとめ整えることがもっとも難しく、したがって当然それがこのゲームの目標となり、そしてそれを実現しているからこそ「The quick brown fox ~」は模範例とみなされてきたのです。
英文としていたって平凡な「The quick brown fox ~」が代表作であることに、パングラムのなんたるかが端的に示されている、という言い方もできるでしょう。
完全パングラムとかなパズル
ところで、「The quick brown fox ~」のように同字がいくつか存在するふつうのパングラムに対し、文字が1つも重複していない、たとえば英語ならA~Zの26字のみで完結したパングラムがあり、それは「完全パングラム(perfect pangram)」と呼ばれます。
完全パングラムを「当該言語の基底をなす一定数の文字を過不足なく用いて、詩歌や文を作る」と定義すれば、難易度がパングラムよりずっと高まるのは容易に想像できるでしょう。じじつ完全パングラムの条件下では、「The quick brown fox ~」もまったく成り立ちません。
*
難易度のことはさておいて、完全パングラムの条件に注目すると、ジグソーパズルと同じ原理であることが分かります。100ピースのパズルが100コ全部のピースを満遍なく組み合わせて完成するように、英語ならアルファベット26コちょうど、日本語ならかな46――文語は「ゐ」「ゑ」を加えた48――コちょうどででき上がるからです。
そこで、完全パングラムとパズルとの類似性に着目した私は、日本語のパングラムに一般名称がないこと、また「いろは歌」がどれほど有名にせよいち作品に過ぎないものを代名詞的に使用するのはおかしいこと、を勘案し、このことば遊びをかなのパズル略して「かなパズル」と命名しました。
*
そもそも、50弱のかなはひと通りの詩歌や文を作成するに十分な字数であり、「あめつちの詞」「たゐに」「いろは歌」「とりな歌」といった歴代作品が完全パングラムの形式で作られているように、「パングラム」の呼び名はもとより正確でありません。といって「完全パングラム」といちいち「完全」を冠するのはまどろっこしく、内実も伝わりにくい。
そういう点からも、「かなパズル」なら名は体を表しており、シンプルで、呼称にふさわしいのではないでしょうか。
パングラムは通称として
日本語のパングラムを「かなパズル」と名づけた理由は、おおむね以上のとおりです。
ほかにも理由がありますが、それについては別の機会にお話ししたいと思います。
*
さきほど述べたように、「いろは歌」に代表される日本語のパングラムはほんらい完全パングラムと呼ぶべきです。
ただ、そこまで厳格に意識している人は少ないでしょうし、ふだんはパングラム=完全パングラムという認識で問題ないでしょう。
*
ということで、このことば遊びの呼び方について、当サイトでは基本的に「かなパズル」を使いますが、日本語によるパングラムとは完全パングラムのことを指すのだとしっかり確認したうえで、通り名としての「パングラム」も併用していきたいと思います。
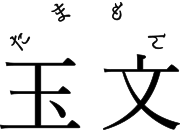
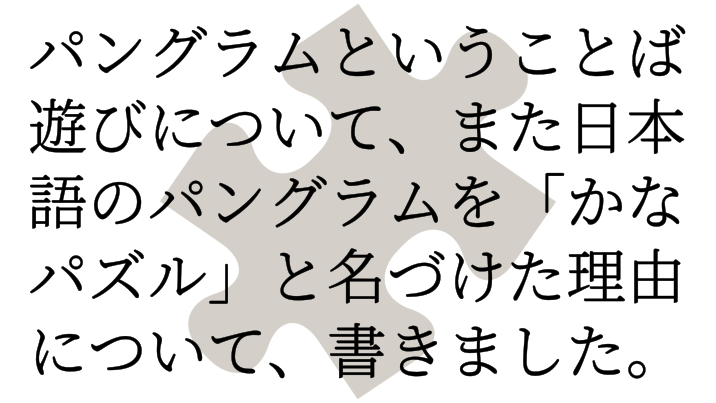
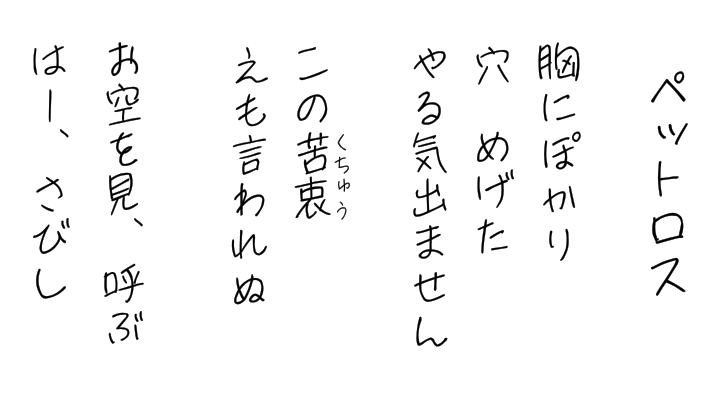

コメント