パングラムは難解です。どこが難しいのでしょうか。
難しさの理由
パングラムは、ことばを用いた難解な頭脳ゲームです。
使うのは50字に満たないかなにもかかわらず、とかくまともに通用する日本語になりません。
ことばづかいがおかしかったり文意がちぐはぐだったりと、程度の差はあれどこかしら不自然な表現-意味内容になってしまいます。
私も作るようになってしばらくの間、日本語が好きだと自認する母語話者としての矜持を失いそうでした。
*
パングラムの難しさを一言すれば、不可測性ということになるでしょう。
そして不可測性の原因は、ほかでもない「あ〜ん全てのかなを過不足なく用いる」ルールです。
このルールによってことばの扱いが拘束され、文脈が流動し、ことばづかいや文意を思うようにコントロールできなくなります。つまり、ことばの拘束と文脈の流動が相俟って進み行きが不可測になるということです。
だから難しい。
拘束性
ことばの拘束性について考えてみましょう。
たとえばサッカーを話題に作成するさい、「キック」と「キーパー」で「き」が、「ドリブル」と「シュート」で「と」が、「ボール」と「ゴール」で「る」が、というように、関連する語を思い浮かべると名詞だけでもかながつぎつぎ重複していきます。おのおの片方しか採用できず、「ドリブルからシュート」といったよくあるフレーズも使えません。
むろん他の品詞も加わるので、かなが重複する率はさらに高まります。
*
また、重複の禁止と併せて、全部をもれなく使い切るのがパングラムでした。”今回は「え」と「ほ」と「や」が余りました” というわけにはいきません。
重複を避けることにばかり意識を向けておられず、同時に1つも余らさぬべく不断の配慮が求められます。
それが身動きをいっそうとりにくくするのは想像に難くないでしょう。
*
こうして語の選出が拘束され、文句の形成が拘束され、ことばづかいを適切に構成できなくなる。
流動性
つづいて文脈の流動性です。
さきほど、パングラムでは「語の選出が拘束され、文句の形成が拘束され、」と述べましたが、この状況は作成中ずっとつづきます。
見方を変えると、文脈が流動して内容の筋道が定まりにくいということです。ふつう詩文を書く場合、多少なりとも頭のなかに構想があり、それにもとづいてことばを紡いでいくでしょう。対して、パングラムは予測できない仕方で文脈が転じていきます。まえもって具体的な筋立てを思い描いても、その通りになることはまずありません。
*
小説の世界で「物語の先行きは作家にも分からない」といわれることがあるし、気ままに文章を書き出して話が変転していくこともあるけれど、これらとは事情が異なります。流動的であるだけなら、どのような展開になろうとそれ以前の内容と矛盾しないようことばを継いだり、あるいは全体の結構を手直ししたりと、必要に応じて文意を整えることができるでしょう。ところが、パングラムではことばの扱いが拘束されているため、「必要に応じて」がおいそれと叶わないのです。
*
自分の意思で文脈を制御できず、流れに翻弄され、その結果てんで筋が通らないという事態も起きてしまう。
拘束性×流動性=不可測性
かなの数が少なくなるにつれ、ことばの拘束は締め付けが強くなり、文脈の流動に対応するのもより困難になります。
たとえば8割ほど組み合わさったとして、じゃああと2割だからもう少しで完成だ、という具合にはすんなりいきません。
残った2割のかなで、8割の部分と表現-意味の整合する語句を作り出さなければなりませんが、残ったかなというのはそれまでに使いどころを見つけられなかったいわば余りものです。これら全部がピタリと組み合わさることなどそうそうないのは、作った経験のある方ならよくご存じでしょう。
*
残りのかなで適当な語句を作れないと、かなを補うため、すでにある語句のうちのどれかを捨てるなり変形するなりする必要があります。そうすると、せっかく整っていたことばづかいや文意に変容を来し、新たな問題が生じかねません。それが大半といってもいいでしょう。
最悪の場合には、残り数文字のところからこれらを組み合わせるための調整が芋づる式に連鎖し、ほとんどやり直しに近い状態まで解体されることもある。
じっさいに経験していますが、そのときはなんともいえない虚脱感に襲われました。
*
このように、ことばの拘束と文脈の流動が掛け合わさることで進み行きが不可測になり、作成過程はあちらを立てればこちらが立たずになって錯綜します。最後の1字が布置されるまでは気を抜けません。
パングラムの目標である「自然な日本語に整える」が難題として立ちはだかるのは、理の当然というべきでしょう。
不可思議なパズル
さて、パングラムとジグソーパズルの原理的な共通性から、私は日本語のパングラムを「かなパズル」と名づけましたが、両者には大きな相違があります。
同一のジグソーパズルを何回やっても、でき上がるのは必ず同一の図柄です。作るたびに図柄がガラリと変化する、そんなパズルは存在しません。
というのも、ジグソーパズルは各ピースがフレーム内のどこに収まるかが最初から100%決まっているからです。拘束性のみ存在し、流動性もなければ不可測性もありません。
あらかじめ位置の固定した絶対的な拘束性は、かえって解くうえでのヒントになっているともいえます。この点では、マスに入る正解のかなが1つと定まっているクロスワードに似ているでしょうか。
*
いっぽう、かなのパズルであるパングラムは、毎回内容が様変わりします。
使用するのはいつも同じあ~んの46――文語は48――コなのに、作成するごとにこれらの配置は驚くほど変わり、まるで違った図柄――日本語表現――が形作られる。
ご説明してきたとおり、拘束性に流動性が重なって不可測性が生じ、作り手も予想だにしないことばづかいや文意が編み出されるからです。
といって、コントロール不能に陥るがままかなが組み合わされ、ヘンテコ、デタラメな表現-意味内容になるということではありません。くまなく明瞭な図柄――判然とした日本語――でなかったら、パズルとして不良品でしょう。
常識的に通じる、自然な日本語とみなされる範囲のなかで、作り始めたときには思いもつかなかった多様な詩文が描き出されるということです。
*
パングラムは、事前に正解が存在しません。かなを組み合わせていくのと同時一体的に文意が生成され、途中でかなの組み合わせが変わればその都度内容が変動します。全部のかなが組み合わさるまでは、フレームの形も確定しません。そしてひと通り組み合わさり、一字一句瑕疵のない日本語であることが確認されると、初めて正解――の1つ――だったと分かります。作り手も “なるほど、そういうふうになったのか” と半ば事後的に感心(?)する。
全てのかなが有機的に連関してうごめき、でき上がる瞬間まで全体像を明らかにしないのがパングラムというパズルなのです。その実態から、さしずめ「動的パズル」と表現してもいいでしょうか。
そして、動的な込み入った状況下でいかに臨機応変にまとめ整えるかに、作り手のウデが試されるわけです。
*
原理は共通していてもジグソーパズルよりパングラムのほうが隔絶して難解であることは、これまでの論からご納得いただけると思います。
もちろん、ジグソーパズルでも色形の似通ったピースの識別がしにくいとか、ピースの数が多くなると量的な面で難易度が増す――完成までに時間がかかる――とかいったことはあるものの、そこでなされる思考は比較的単調です。ピースが埋まるにつれてより簡単になり、ペースも上がります。
それに比べ、パングラムはもっとずっと複雑に微細にバランスよく思考を巡らさねばなりません。進むほどに難渋し、ペースは低下・停滞します。後退することもしょっちゅうです。
しかし、難しいのは確かにせよ、どういう図柄になるかが未知のパズルって、つねに新鮮で、すごくスリリングで、とても魅力的だと思いませんか?
難しいから面白い
拘束性と流動性によって進み行きが不可測であるといっても、きちんとした日本語に整えることが不可能なのではありません。ゲームの多くに不可測性はつきものですが、わけてもパングラムは不可測性に間断なく見舞われ、非常に入り組んだかなの操作が要求されるということです。
有り体にいってしまえば、たかだか50弱のかなを並べ替えるだけ。母語話者ならみな日本語のマスターであり、誰もが不可測性をかいくぐって的確にかなを整序し得るはずです。
ただし、何事においても当てはまることですが、相性や才能の問題はあるでしょう。パングラムを解くにはパングラムに適した脳ミソの働かせ方が不可欠です。柔軟な思考力はむろん、不可測性――さきの見通せない不安定な状況――に耐える力も欠かせません。外来表現の「ネガティブ・ケイパビリティ」が以前話題になったけれど、日本語には古く「根気」という素敵なことばがありました。
*
1字も疎かにさせず、ああでもないこうでもないとかなを組み合わせていく煩雑な過程は、楽しさより苦しさが勝ります。
でも、粘り強く思考を重ねることが、ことばを用いた知的なゲームの佳境であり真髄でしょう。”もうダメだ、どうしても不自然になってしまう” と行き詰まってからがいよいよ本番、といったところでしょうか。
*
とことん悩み抜いて幾度も障壁を乗り越えてこそ、一点の曇りもないかなのパズルが眼前に現れたときの感慨もひとしおです。
おしまいに、本稿における「拘束(性)」と「流動(性)」は、どちらでも成り立つ箇所があります。話がややこしくならぬよう、「ことばの拘束」「文脈の流動」とで使い分けました。
また、厳正にみればパングラムでは全てのかなが互いを制約し合う――支え合う――関係にあり、あ~んのかな1字1字に拘束性が備わっているといえますが、この点についてはまたの機会に言及したいと思います。
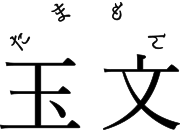
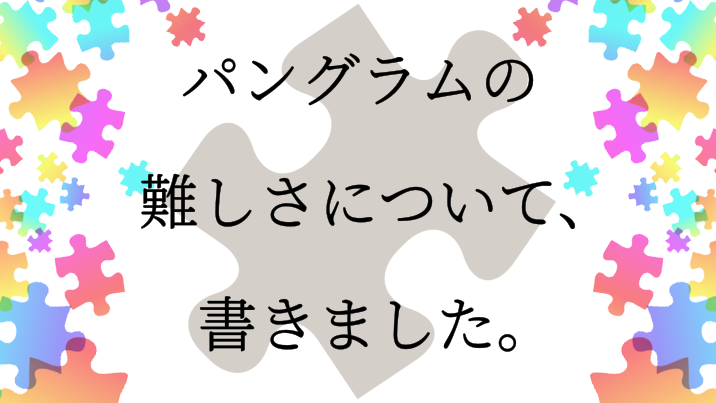
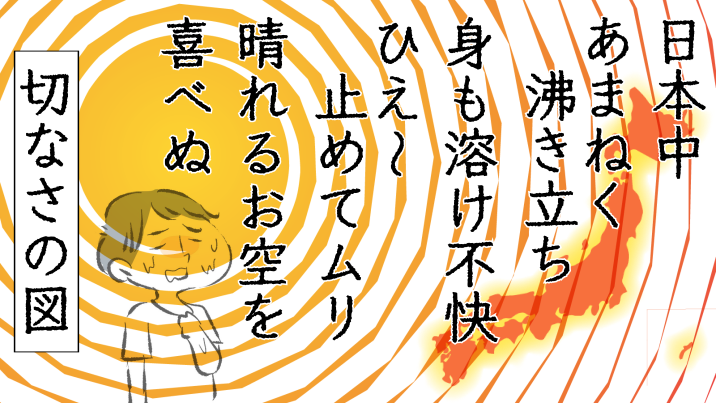

コメント