- 祭りへ行けば 例の路地に 出店並び居 お面綿菓子 遊ぶや踊る 幸生む声す えも寝ぬ夜祝ぐ
- まつりへゆけば れいのろぢに でみせならびゐ おめんわたがし あそぶやをどる さきうむこゑす えもねぬよほぐ
祭りへ行くといつもの路地に出店が並んでいて、お面や綿菓子が売られ、会場では遊び回る子や踊っている人がいる。幸せを生む華やいだ声が響きわたっている。とても寝られないような素晴らしい夜を祝福するよ。
ある夜の祭りの情景です。
語法と内容について。
「例の路地に」の「例の」は「いつもの(ように)」という意味で、古文では頻出です。また、「ろぢ」には「露地」もあり、いずれも現在の「路地」および「露地」とはじゃっかんニュアンスが違うらしい。意味としてはどちらでも問題がないので、ここでは「路地」にしました。
*
「出店並び居 お面綿菓子」の「出店」や「お面」、「綿菓子」は古語にありません。しかしながら現代のことを文語で描くさい、名詞に関しては現在のことばを使用していいでしょう。
「並び居」の「居」は「居る」の連用形です。「居る」は動詞に接続すると補助動詞になり、「~している」という意味になります。
*
「お面綿菓子 遊ぶや踊る」では、「お面」「綿菓子」「遊ぶ」「踊る」と祭りのあるあるを列挙しました。もちろん「お面」と「綿菓子」は直前の「出店並び居」を受けて。人気キャラクターのお面は定番の光景でしょう。大きくてフワフワの綿菓子には特別感があり、買ってもらうのが楽しみでした。
「遊ぶや踊る」の「や」は語調を整える間投助詞で、とくべつ意味はありません。
*
「幸生む声す」の「幸」は「さき」と読み、ほかにも「幸(さきは)ひ」などと使われます。いっぽう、『古事記』の「海幸彦」「山幸彦」はどちらも「さち」です。「さき」のほうは今ではほとんど見聞きしませんね。
*
「えも寝ぬ夜祝ぐ」の「えも寝ぬ」は「え(も)~(打ち消し)」で、意味は「~できない」です。口語では「えも言われ(言え)ぬ」だけ残りました。
*
終わりの3句がすべて終止形なのは偶然ですが、いい感じで収まったと思います。
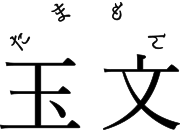

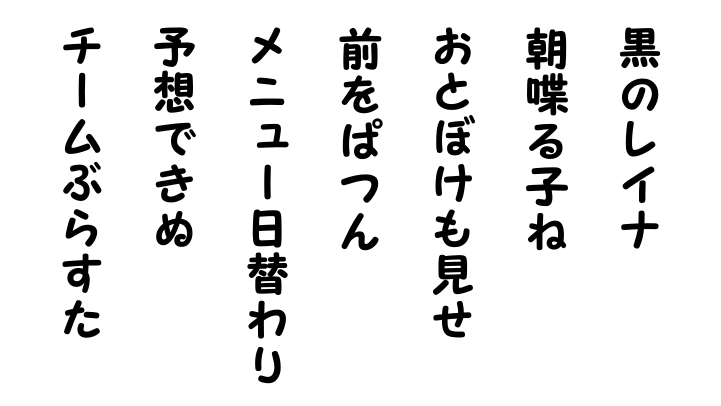
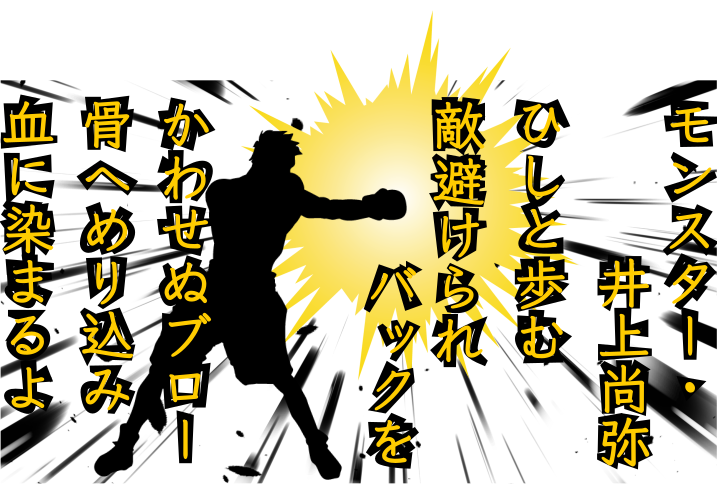
コメント