- ヒッポこわい のろそうな見目も 油断をせずに ガバと口開け むしられる 泳ぎ不得手さ 減り止まぬね
- ひっぽこわい のろそうなみめも ゆだんをせずに がばとくちあけ むしられる およぎふえてさ へりやまぬね
カバは怖い。一見のろそうな姿にも油断をせずに。捕まったらガバと口を開けてむしられる。ところで、泳ぎは不得手さ。また、悲しいことに個体数の減少が止まないね。
カバです。
カバとサイが好きで、こちらのほうが話題が広がりやすいだろうと、カバを選択しました。
内容に沿って、カバの生態のご説明を。
カバというと、いっぱんにのんびりしたイメージが抱かれていると思います。見た目もそうだし、カバをモチーフにしたキャラクターもたいていそんな感じでしょう。
でも、じっさいのカバは相当に危ない。生息地のアフリカではもっとも恐れられる野生動物で、毎年数百人が犠牲になるそうです。縄張りに侵入されて怒るのは分かるけれど、いつどういう行動をとるかの予測が専門家にもつかないらしく、海外のドキュメント番組ではつねに警戒が必要だと地元の住民が語っていました。しかもあれだけの巨体――体重数トン!――なのに時速40~50キロで走るため、狙われたらとても逃げ切れません。1~3句。
*
カバが口を大きく開ける姿は、どなたもご覧になったことがあるでしょう。顎周辺の骨格構造が人間と異なり、180度に近い角度で開くことができます。また、歯はたいへん強大で、噛む力も哺乳類屈指です。鎧のような強靭な皮膚をまとったワニでも真っ二つにされてしまうというから、人間の身体など文字通り「むしられる」でしょう。じじつ遺体もバラバラになっていることがあるといい、想像するだに凄惨な光景です。4・5句。
*
おもに水のなかで暮らしているにもかかわらず、ほとんど泳げません。ヒレの付いた流線形の魚類ならまだしも、四足動物であんなに重たいとなると、たしかに泳ぐには不向きでしょう。水中では水底を歩いて移動し、映像などで泳いでいるように見えるのは水底を蹴った反動で浮いている状態です。それでも案外速いらしく、舟に乗っているところを追いかけられて襲われることも珍しくないとか。6句。
*
大半の野生動物の例に漏れず、カバも個体数が減っており、サイと比較すればずっと数は多いものの、絶滅危惧種に指定されています。人間の活動による環境の変化、牙や肉を狙った密猟が原因と考えられ、たいていは私たちが関与している…。とにもかくにも、より多く生存してほしいです。7句。
語法について。
「ヒッポ」は「hippo」、カバのことです。愛嬌のある響きだし余りやすい「ほ」を含んでいるしで、最初からキーワードに設定していました。
「ガバと口開け」のオノマトペ「ガバ」はもちろんカバに掛けて。
「ヒッポこわい」と「ガバと口開け」は当初から浮かんでいたフレーズなので、そのまま使用できて満足です。
*
この作品を作ったのはずいぶんまえですが、「止まぬ」があることに気づきました。前回は「止めて」、前々回は「止められぬ」。
自作を改めて通覧してみると、ほかにもけっこう見られます。
これまでまったく自覚していなかったけれど、どうやら私にとってつい使いがちな、クセのようなことばなのかもしれません。
前回も記したとおり、同じ語句をできるだけ使わないようにするのが作成するうえでのポリシーです。
今後はちょっと意識して使用を「止め」ねば…。
最後に作成について。
終盤に差しかかった段階で「ぬ」を用いた語句が「やまぬ」しか作れず、これをいかに組み込んでいくかで苦慮しました。候補にあった「減り止まぬ」も、内容と結びつけることができなかったのです。
しばらく悩むなか、ふと個体数減少のことが頭をよぎり、上手い具合に収まりました。
*
かなパズルを成功させるうえでは、かなを巧みに組み合わせる頭の柔軟性だけでなく、テーマについての具体的な知識が重要になります。
たびたび述べていることを、本作では我ながら強く実感しました。泳ぎのことに関しても同様です。
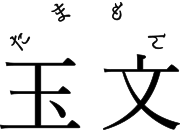

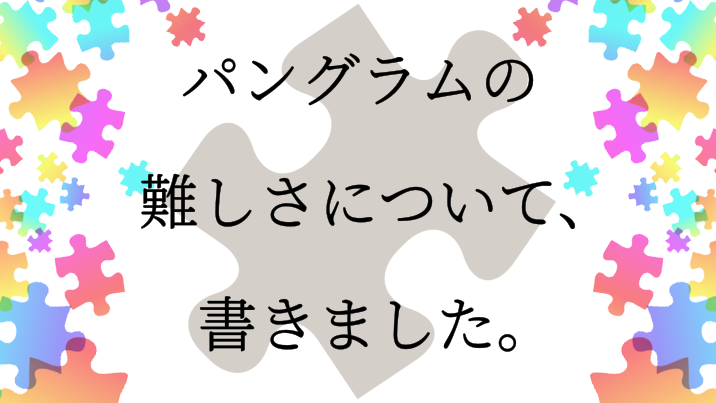
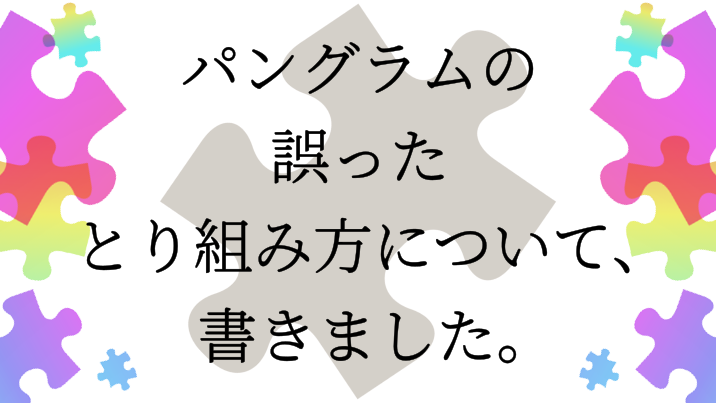
コメント