- 雲ぷかり 広い空へ 急な雨 私は濡れる ぽつねんと 街の声に 背を向けて さ、お休みよ
- くもぷかり ひろいそらへ きゅうなあめ わたしはぬれる ぽつねんと まちのこえに せをむけて さおやすみよ
雲がぷかりと広い空へ浮かび、急な雨が。私は濡れる、ぽつねんと。そんなときは街の声に背を向けて、さあお休みよ。
詩であることを意識して作成した作品です。
記憶するかぎり、詩を書いたことは人生で1度もありません。詩でなにごとかを表現するという性向を自分のなかに微塵とも感じないし、詩を理解するのも苦手です。
かなパズルで詩的な作風になることはあっても、それはこのことば遊びの形式に導かれ結果としてそうなったもの。
でも、ということは、かなパズルを利用すれば自分にも詩を自覚的に作ることができるかもしれない。
そんな思いを抱きつつ、やる気が冷めぬうちにと試みることにしました。
作成について。
金子みすゞの詩を読んでいて気分が高まったのが事の始まりです。
だから、とっかかりも彼女の詩の雰囲気に身を委ねるように。するとほどなく「広いお空へ 雲ぷかり」と浮かんできました。しかし、それ以外はまったくの白紙です。そこでこの2句をキーワードに据え、あとは余った文字群とにらめっこしながら、詩にすることだけを念頭に、自由連想に任せて進めていきました。
おもしろいのは、つづけざまに思いついた「背を向けて」でしょうか。一見するとさきの2句と組み合わせられそうにありません。けれど、なにか感じるところがある。このような予感はときに奏功するので、とりあえずこれもキーワードに設定してみました。また、いつか使いたいと考えていた、余りやすい「ね、ほ」を含む「ぽつねんと」が活かせそうだと直感し、同じくキーワードに採用。
あれやこれや苦慮しつつ、都合3時間ほどででき上がりました。最初に浮かんだ2つの句は少し形が変わったものの、キーワードをすべて採り入れることができて満足です。
詩的表現について。
当初、「雲ぷかり 広い空へ」はその通りに現実の事象を表すつもりだったのが、文脈の都合で比喩表現になりました。
詩といえば比喩がよく用いられますが、比喩を含めて詩のなかには、なにを言わんとしているのかを少なからぬ母語話者が把握できないエキセントリックなことばづかいがなされ、文意の全体像も見通しにくい作品があります。むろんそれは意図的にであり、常識的でないことばの組み合わせ方によって定型的でない物事の捉え方を描き出すためなのでしょう。また、多義的な解釈の可能性に開かれている場合もあるかもしれません。
いっぽうで、かなパズルの眼目はまったく正反対に、いたってふつうの日本語表現を織りなすことです。「あ~んのかな46文字を過不足なく用いる」ということばの扱いに厳しい制約の課された状況にあっては、ことばづかいなり文意なりに不自然さが生じ、母語話者が違和感を覚えることのないごく標準的な日本語表現を形作ることこそがもっとも難しいのですから。換言すれば、ことばづかいは一般的な規範に則り、文意も一義的な理解に収まるよう最大限注力することに、このことば遊びの要諦があるわけです。してみると、ふだんわれわれが詩――や歌や散文など――をものするのとは目指すところがまるで違うことが分かりますね。
したがって、かなパズルで詩を作ったり比喩を用いたりするのなら突飛な表現は避け、常識に照らして――または必要最低限の補足説明により――読み手の納得が得られるものにするべきでしょう。加えて、解釈に異議が出そうな場合に説得力をもたせるには、ふだんのかなパズル作品が明瞭な意味内容であることも重要になります。そうでないと、まっとうな日本語表現に整えられずただデタラメに並べた語句の羅列を、苦し紛れに「詩的表現」と称しているだけだとみなされ、反論もできません。
かなパズルと純粋な詩とでは前提も意義も異なります。詩である以前にかなパズルであること、すなわち「かなパズルとしての詩」であることを忘れないことが肝要でしょう。
内容と語法について。
さて、1~5句は心のなかの比喩です。「広い空」である心に「雲」が「ぷかり」と出現し、「急な雨」が降って「私は濡れる」、「ぽつねんと」。
ここで表現したいのは、日々の生活でイヤなことが蓄積して精神的にどんよりし(=雲ぷかり)、ある日それが一気に表出して(=急な雨)落ち込む様子(=私は濡れる)です。「私は濡れる」については、あるいは涙に暮れることと解するのもいいでしょうか。かなパズルにおいて多義性のある表現はよくない、一義的な内容であるべきだ、とさきほど述べたばかりです。ただし、それは作り手に恣意的な主張を許す悪い意味での曖昧さを批判しているのであって、それぞれが適切な文意をなすうえでの選択的な豊かさであればもちろんかまいません。
序盤でキーワードに掲げていた、1人寂しいさまを意味する「ぽつねんと」はいかにも詩に向いたことばで、内容ともしっかり噛み合って使用することができました。
つづく6句目「街の声」も比喩であり、街頭インタビューの意見のことではありません。街の声=街のにぎやかさ=社会が活動している証、ということで、社会生活のさまざまを表しています。そこに気落ちする要因が含まれていることも少なくないでしょう。
6句を併せた後半部分をまとめると、精神的に疲弊して辛いときは、社会の喧噪をほっぽり出して(=街の声に背を向けて)少し休みなさいよ(=さ、お休みよ)、となります。なるほど、「背を向けて」にはこういう役割があったんですね。
初めて挑んだ詩は、そのほとんどが比喩で構成されることになりました。
詩の語句をいちいち具体的に解説するのは野暮なことかもしれません。でも、ここまでいろいろお話ししてきたように、かなパズルということば遊びの性質を考えたとき、ことばづかいにも文意にもあやふやさが一切ないとはっきりさせることが必要でしょう。そのため、すべての語句に説明を付しました。
心の動きを天候に例えるのは詩にかぎらずおなじみの方法だし、「街の声」も擬人法としてべつだん風変わりでなく、一連の比喩は穏当なものだろう。私はいち母語話者としてそう考えます。
いかがでしょうか。
かなパズルの力を借りた詩への挑戦は思いのほか楽しいものでした。
かなパズルを作り始めて以来、その魅力に大いにハマっているとはいえ、純粋に楽しいかと問われて楽天的にハイとは即答しがたいところがあります。作成にとりかかるまえは “ああ、これから苦難の時間が始まるな” と少しばかり憂鬱な気持ちになるし、じっさいに作成中は苦しみの連続です。いくら試行錯誤しても出口が見えてこないと腐した気分になってくる。
ところが、今回も袋小路に何度か迷い込んだし脳ミソもしっかり疲れたけれど、不思議とずっと明るい心持ちでした。詩にはおよそなじまないと思っていた自分が詩作している、そんな状況がおかしかったのかもしれません。
ただし、調子に乗って詩に意識が偏るとかなパズル作りに悪影響を及ぼしそうです。だからしばらく間を空け、いずれまた機をつかまえてとり組んでみたいと思います。
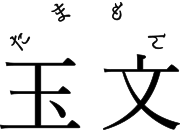

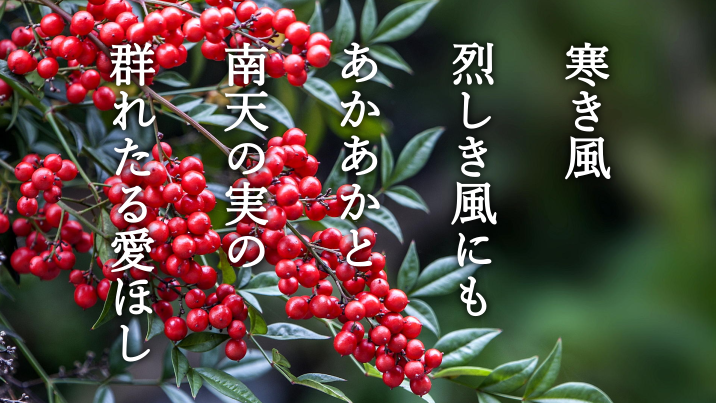
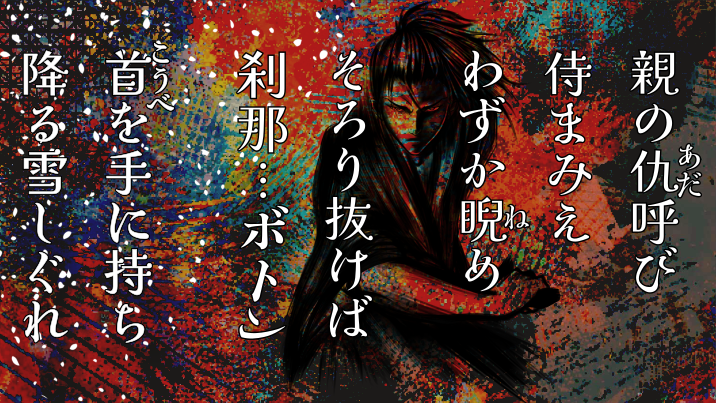
コメント